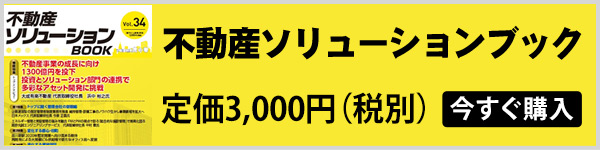不動産トピックス
【今週号の最終面特集】識者に聞く 都市における災害への対応
![]() 2023.09.04 10:17
2023.09.04 10:17
首都直下の被害想定は減少も課題は山積 民間ビル含め周辺との連携で被災者の安全確保
1923年9月1日に発生した関東大震災から100年が経過した。そこから現在に至るまでにも、東日本大震災や阪神淡路大震災など多くの地震災害が起き、水害など地震以外の災害も頻発している。現代の都市における防災への考え方を今一度見直してみたい。
外国人旅行者の安全確保 高経年マンションの建替え問題も
インバウンドの受け入れが再開され、大都市では外国人旅行者の数がコロナ禍前の状態に戻りつつある。一方で懸念されるのが、地震などの大規模な災害が発生した場合における外国人旅行者の安全確保の問題である。一般的に、高齢者や障がい者、乳幼児といった人々は災害時に配慮や介助が必要な災害弱者とされており、災害が起きた際には周囲の人々が支え合いながら特段の配慮が必要とされる。しかし海外からの旅行者の多くは健康面でハンデを抱えているわけではなく、ここでいう災害弱者には当てはまらない。だが、とりわけ地震へのリアクションは日本人と外国人で異なる部分もあるようだ。
東京都では過去の経験を踏まえ2013年に帰宅困難者条例を施行し、民間のビルを含む一定規模以上の施設において帰宅困難者の一時的な受け入れを求めている。旅行中に災害に見舞われた外国人の安全確保や的確な避難誘導を実現するために、アナウンスや案内表示の外国語対応は民間ビルにおいても取り組みたいところである。
2011年の東日本大震災では都内でも震度5強を観測し、多くの課題と教訓を残した。公共交通機関の機能不全はその代表例といえる。発災当時、大半の鉄道駅は構内の混乱を防ぐために入口を閉鎖。その結果、人々は一時避難ができる場所を求めて屋外をさまよう事態となった。この経験を生かし、各鉄道事業者はトイレなどの一部施設の開放など臨機応変に対応できる災害時のマニュアル構築に注力している。元東京都副知事で令和防災研究所(東京都千代田区)の所長を務める青山佾氏は「都市部では駅と直結した施設も多く建築されています。人々に屋根のある一時避難場所を提供するためにも、鉄道会社と駅周辺の民間ビル事業者が災害対応に関する連携の強化が求められています」と述べる。
1923年の関東大震災は、関東地方の南方沖にある相模トラフにおいて引き起こされた。発生が危惧される首都直下地震も、この相模トラフが発生源になるとされる。東京都心は強固な再開発ビルが次々と誕生し、都市機能の更新が日々続いている。都心に勤めるオフィスワーカーは地震発生直後、堅牢な躯体と数日分の備蓄品を備えたオフィスビルに留まることが望ましい行動といえる。東日本大震災の折には帰宅困難者に加え、都心に勤める人々を迎えに行く自動車が渋滞を引き起こし、緊急車両の通行を妨げるケースも散見された。東京都が指定する緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化は約90%まで達しており、2022年に報告された首都直下地震の最新の被害想定は10年前に比べ人的・物的被害が6割程度減少している。一方で青山氏は「今後、郊外部の高経年マンションの建替えが大きな問題となる可能性があります」と指摘する。
全国に立地するマンション約650万戸のうち、およそ4分の1が都内に集中しているとされる。また新耐震基準で建築されたマンションのうち築40年を超える物件は、15年後の2038年には260万戸と、現在の8倍までふくれあがるとされている。特に郊外部は大手の資本が入りにくく、建替えは住民の負担が大きくあまり進んでいないのが現状。マンションの建替えをスムーズに実現する法整備が行われているものの、住人が減り始めた郊外部の高経年マンションの実態に即しているとは言い難い。青山氏は「高経年マンションの除却や管理組合の解散の仕組みづくりが必要です。またマンションとしての運用が難しい場合はシェアオフィスなど他用途への転用も視野に入れた改修を検討するのも一案です」と述べる。ビルオーナーは保有物件の安全性を再確認するだけでなく、周辺に倒壊などの危険性がある高経年マンションがないかどうか、災害時の被害想定をシミュレーションしながら検証する必要があるだろう。
オフィスの在席状況に合わせ臨機応変な対応が必要に
多くの人が働くビルでは、比較的公共性の高い物件も数多く存在するし、用途や所有形態などで場合によっては外部からの来館者を招き入れるような事態もおこる。建物の事情によって防災対策の手法が変わるだけに、基本的なポイントはまず押さえておきたいところだ。
例えば企業が自社の事業活動のために建物を保有・運用する、いわゆる自社ビルの場合、災害時の初動対応から事業継続に至るマネジメントは従業員に対しての防災計画だけでなく、建物そのものの運用計画についても自社の事業継続計画(BCP)に沿って自社ですべて完結させることができる。一方、テナントが入居する賃貸ビルの場合では、共用部分における防災対策は基本的にビルオーナーが担うことになり、テナントとして入居する企業ができる防災対策は主として専有部分に限定される。テナントは退去時に貸室を原状回復するのが一般的なので、什器の転倒防止対策も消極的になりがちだし、躯体や構造に干渉するような大掛かりな工事は非常に難しい。そのため賃貸ビルに入居する企業にとっては、防災に関して自社の判断で対応可能な範囲の対策が何か。そして、どうすればその範囲を拡大できるかを考えることが、従業員の生命を守りBCPを実行する上で重要となるといえる。
また、新型コロナ感染拡大によって働き方は大きく変化した。その最たる例が自宅など本来のオフィス以外の場所で仕事をするリモートワークの普及である。コロナ禍が収束した現在においても、オフィスへの出社をベースとしながらも一部リモートワークを導入している企業は多い。リモートワークの定着は企業の防災対策にどのような影響を与えるか。ビル減災研究所(東京都千代田区)の田中純一代表理事は次のように話す。
「企業は従業員の生命や安全を守る場としてオフィスの機能を考えています。にもかかわらず従業員が安全性の担保がない就業場所で仕事を行い、その時に大きな災害が起きて負傷したり安否確認がとれない状況となってしまっては、せっかく安心安全な場所として用意したオフィスが生かされないことになります」
コワーキングスペースは都市部を中心にその数を急激に伸ばし、最近では住宅地の商業施設内にも出店例が増え、利用者の多様なニーズに対応している。しかし災害時の安全確保が十分であるか、利用する従業員側、管理する企業側は改めて確認する必要があると田中氏は指摘する。特に留意すべきなのが、東京であれば都心部の外周にドーナツ状に広がる住宅メインのエリアで、具体的には山手通りから環状7号線にかけての木造住宅が密集するいわゆる木密地域である。このエリアは都心に勤める従業員の居住地域となっていることから、自宅近くで仕事ができるコワーキングスペースが多数存在する。だがこのようなエリアは東京都の被害想定において建物倒壊や焼失など大変危険な地域とされている。リモートワーク先を選ぶ際には自宅からの距離や利用料金などで安易に選ぶのではなく、災害発生時に建物や室内の安全が確保され、無事帰宅できる安全性が担保されているかどうかを見極める必要がありそうだ。
またリモートワークの普及によってオフィスの出社率が一定ではなくなった今、どのような場面においても避難や人命救助、事業継続ができる自衛消防組織の体制づくりが求められている。前出の田中氏は「出社人数の減少で曜日や時間帯によってオフィス内のシチュエーションが異なるため、防災訓練はあらゆる場面を想定して実施する必要があります。また災害対応に係る権限を特定の人間に集中させることなく、発災時にオフィスに在籍している人間だけで的確な行動がとれるよう、オフィス在籍時またはリモートワーク時の従業員ひとりひとりの役割を見直すことが重要です」と述べる。
英語対応で的確な避難誘導を
元東京都副知事 令和防災研究所 所長 青山佾氏
日本を訪れた旅行者の多くは日本人のように日頃から地震を体験しておらず、微細な揺れであってもパニックを起こしてしまうケースが考えられます。外国人旅行者への災害対応において問題となるのが、言語の違いと正確な情報伝達です。安全な避難誘導を行うためにも、英語による的確なアナウンスでまずは心を落ち着かせることを重要です。
従業員のリモート先を把握すべき
ビル減災研究所 代表理事 田中純一氏
東日本大震災の折に問題となった帰宅困難者については、在宅勤務であれば従業員の安全確保という面でプラスに働くかもしれません。一方、リモートワークをされる方の中には自宅ではなくコワーキングスペースなどを利用するケースも多くみられます。企業として組織的な災害対応を実践するためには、どの場所でリモートワークを行っているか、従業員ごとに把握する必要があると言えます。